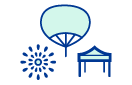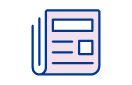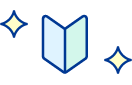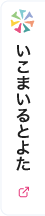結果一覧
-
藤岡
川口城跡
通称「城ケ峰」と呼ぶ山上(比高40m)にあります。矢作川を眼下に見下ろす山稜の頂を削り平にした場所が本丸と考えられています。本丸跡は南北約30メートル、東西10メートル、約3メートル下った南西面には幅5メートル程の曲輪と2か所の堀切跡があり、敵の侵入を防いだと考えられています。
-
足助
中馬館
豊田市足助にある「中馬館」は、稲橋銀行足助支店として建てられた建物を利用した資料館。明治から大正にかけての地方銀行の姿をよく残しており、現在は県の文化財指定となっています。主に足助の証行・金融・交通・町並みの資料を展示しています。
-
足助
心月院
鈴木正三和尚が創建した曹洞宗の寺院。 鈴木正三和尚は、戦国時代の末期に則定城主であった鈴木忠兵衛重次の長男に生まれて、徳川家康、秀忠の二代に仕えました。42歳の時に出家し、禅を唱え、多くの寺院の建立や再建を手がけるなど宗教活動に力を入れました。則定の入り口にある心月院は、厳しく激しく生きた姿を伝える正三像が祀られています。
-
足助
足助八幡宮
古くから足、旅、交通の守護神として信仰されている足助八幡宮。現在では、病気平癒、安産の神としても信仰されています。創建は天武天皇白鳳二年(673)と伝えられ、室町時代の建築様式を今に伝える本殿が、国の重要文化財に指定されています。また、文化財も数多く遺されており、1612年(慶長17年)に奉納された「鉄砲的打図板額」は、県の文化財指定。鉄砲を描いた古い絵馬は全国でも数枚しか遺っておらず、この絵馬は東京オリンピックにおける射撃競技のプログラムの...
-
足助
広瀬重光刃物店
鉈や鎌、鍬など山仕事で使われる野鍛冶として始まり、代々受け継がれた技は刀匠としても指折りで、昭和27年には政府依頼の講和記念の日本刀もつくるなど大仕事もしてきました。現在は、7代目友門によって包丁、ナイフ、鉈、鎌などの手打刃物の製作、又農具などの修理、刃物の砥ぎ・修理なども行っています。
-
足助
馬頭観音
新町の入り口には、馬頭観音、不動明王、大日如来、行者さまなど、数多くの石仏が祀られ、松尾芭蕉の句碑も江戸末期に足助の俳人「板倉塞馬」が建立されています。 「馬をさへ ながむる雪の 朝(あした)かな はせを」
-
足助
宝田山 昌全寺
愛知県指定文化財 木造観世音菩薩坐像
-
足助
平勝寺
かつて天台宗の寺院として栄えた「平勝寺」。ここには数多くの文化財があり、木造観音菩薩坐像(国指定重要文化財)は平治元年(1159)に造られた桧の寄木造で、高さは1.5m。胎内には墨書銘があります。 17年に1回のご開帳の秘仏。二天立像(愛知県指定文化財) 観音菩薩像と同時代の作。平勝寺扁額(愛知県指定文化財))元徳2年(1330)の作。 かねかけ杉(足助町指定文化財))胸高囲6メートルもある大杉 綾渡の夜念仏と盆踊(国指定無形民俗文化財)8月10日と15日に行われています。
-
足助
宗源寺
曹洞宗 梅洞山宗源寺
-
足助
鈴木正三記念館
郷土の偉人、思想家、宗教家である鈴木正三に関する資料を展示しています。
-
足助
地蔵堂(足助町)
このお堂は本来、紙屋鈴木家所有でしたが、昭和18年香積寺に寄贈されました。 平成27年2月に修復。堂守はいませんが、有志によって管理しています。 本尊の地蔵菩薩は珍しい座像。ほかにも願いを叶えてくださる「抱き地蔵」と、痛いところと同じ部分をさすると治ると言われる「おびんずるさん」に出会えます。
-
足助
三州足助屋敷
生きた民俗資料館と言われる三州足助屋敷は、かつての豪農屋敷を再現し、昭和55年に開館しました。 ここでは、かつてこの地域で行われていた「炭焼き」「木地」「機織り」など、暮らしの“手仕事”が行われています。手仕事の中には、体験できるものもあります。
-
足助
弘化2年の道しるべ
中馬街道と遠州街道の分岐にある道標。「ぜんこう寺(善光寺)」「ほうらい寺(鳳来寺)」と彫られています。
-
足助
重要文化財 旧鈴木家住宅(紙屋鈴木家)
国指定重要文化財「旧鈴木家住宅」は、約4,000㎡の敷地に16棟の建物が建ち並ぶ、江戸時代から続いた大商家の屋敷です。 屋号を「紙屋」といい、紙、漆、醸造業や金融業、土地経営で財を成し、江戸から明治にかけて足助の経済や文化を牽引してきました。 令和5年8月から主屋の公開が始まり、当時の建物の様子を見て感じることができます。 主屋の奥では残り15棟の保存修理工事が引き続き行われており、工事の様子を見学できる特別ツアーも行われています。
-
足助
大鷲院
大鷲院は、足助にある霊場。山岡鉄舟の筆による「正法」の額が掲げられた山門をくぐると、参道には見上げるばかりの大石垣が続きます。また、裏山の岩肌には県下では珍しい磨崖仏が彫られ、海抜500mの頂上近くには怪猫伝説を伝える八丈岩があります。
-
足助
宗恩寺
中馬の町並みを見下ろす高台に位置するこのお寺は、足助八景の一つ「宗恩寺の晩鐘」として綺麗な音色を街中に響きわたらせています。