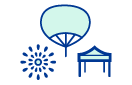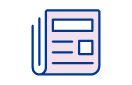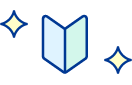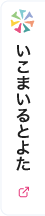結果一覧

このマークのあるイベントはいこまいるが貯まるイベントです。
「いこまいる」とは?


豊田の様々なスポットに出かけたり、イベントやスタンプラリーに参加することで、クーポンや特産品に交換できる観光サービスです。
豊田のお出かけがもっと楽しくなるサービスなので、ぜひご登録ください。
-
 足助
足助
足助みたち栗園
愛知県で唯一、栗拾いが楽しめる栗園です。春には、わらび狩りも楽しめます。 東京ドーム5個分の広々とした敷地で、自然の中でウォーキングを楽しみながら体験できます! 小さななお子様が楽しめる遊具も用意しているので、家族でのお出掛けにもぴったりです。
-
 足助
足助
黍生城
平安末期、標高374メートルの山頂に、尾張国の山田重長が築いた山城です。 足助に居住後、足助氏を称し、以後、足助氏がこの地を治めるようになりました。 重長は足助氏の始祖とされています。
-
 足助
足助
宗源寺
曹洞宗 梅洞山宗源寺
-
 足助
足助
足助神社
鎌倉時代末期(1331年)に、後醍醐天皇が鎌倉幕府倒幕の旗をあげた「元弘の変」で、笠置山に立て籠ったときの篭城軍総大将・足助次郎重範を祀っています。弓の名手と伝えられています。
-
 足助
足助
鈴木正三記念館
郷土の偉人、思想家、宗教家である鈴木正三に関する資料を展示しています。
-
 足助
足助
地蔵堂(足助町)
このお堂は本来、紙屋鈴木家所有でしたが、昭和18年香積寺に寄贈されました。 平成27年2月に修復。堂守はいませんが、有志によって管理しています。 本尊の地蔵菩薩は珍しい座像。ほかにも願いを叶えてくださる「抱き地蔵」と、痛いところと同じ部分をさすると治ると言われる「おびんずるさん」に出会えます。
-
 足助
足助
豊田市 里山くらし体験館 すげの里
すげの里は、都市と農山村の交流や中山間地域への定住をすすめるため、里山での農業体験や宿泊体験を行う施設。薪ボイラーや薪ストーブ、 太陽光発電など自然エネルギー100%で運営することを目指しています。 豊かな自然の恵みや里に息づく生活の知恵や技をふれるいろいろな講座を開講しています。
-
 足助
足助
Sauna Base SHIFUKU
愛知県豊田市にあるSauna Base SHIFUKUでは、自然の中で非日常のアウトドアサウナ体験ができます。「川の音、鳥のさえずりを聞きながら、そよ風を肌で感じる」日常では味わえないリラクゼーション体験が、ここにはあります。 大切な人や仲間と一緒に、誰にも邪魔されないプライベートなアウトドア空間で「至福」のサウナ体験を楽しみにぜひ足を運んでみてください。
-
 足助
足助
バーバラはうす
足助町で、ZiZi工房とならんで人気の手作りパンのお店「ベーカリー バーバラはうす」。 店内には、元気なおばあちゃんたちが手間を惜しまず焼いた添加物なしのこだわりパンが20種類ほど並んでいます。 バーバラはうすは、レストランや日帰り入浴、介護施設も兼ね備えた「百年草」の中にあります。 持ち帰りはもちろん、店内で頂くこともOK。パンを温め直したり、カットしてもらうこともできます。
-
 足助
足助
観音山
第二の香嵐渓とも呼ばれる、もみじの名所。山頂付近には観音寺があり、木造天部立像は豊田市指定文化財になっています。
-
 足助
足助
ZiZi工房
足助のおじいさん&おばあさんたちが、真心こめてハムやウィンナーを作っているのが、「足助ハム ZiZi工房」です。 人のぬくもりがスパイスだと、厳選された素材を使い、手作りの商品は美味しいと好評で、今や、足助を代表する名物商品になっています。ZiZi工房は、レストランや日帰り入浴、介護施設も兼ね備えた「百年草」の中にあります。 店では、焼きたてのフランクフルトを食べることができ、試食もOK!
-
 足助
足助
飯盛山
愛知130の山にも選定されている香嵐渓の飯盛山。平安時代の終わりごろに足助家初代・重長が飯盛山城を築きました。 北西向き斜面の約0.5haにカタクリの群生地があり、4月上旬まで見られます。 3月中旬頃に暖かい日に一気に開花し、天気の悪い日や、夜には花を閉じてしまいます。
-
 足助
足助
三州足助屋敷
生きた民俗資料館と言われる三州足助屋敷は、かつての豪農屋敷を再現し、昭和55年に開館しました。 ここでは、かつてこの地域で行われていた「傘屋」「木地」「機織り」など、暮らしの“手仕事”が行われています。手仕事の中には、体験できるものもあります。
-
 足助
足助
弘化2年の道しるべ
中馬街道と遠州街道の分岐にある道標。「ぜんこう寺(善光寺)」「ほうらい寺(鳳来寺)」と彫られています。
-
 足助
足助
寧比曽岳
愛知県の北東部に位置する寧比曽岳(標高1121m)は、伊勢神方面の恵那コースと、足助方面の本線コースの2方向に分岐しています。山頂からの眺望もよく、1年を通して親しまれています。東海自然歩道なので登山道は登りやすく、ベンチもたくさん整備されているのでゆったり登山したい方に最適です。
-
 足助
足助
大鷲院
大鷲院は、足助にある霊場。山岡鉄舟の筆による「正法」の額が掲げられた山門をくぐると、参道には見上げるばかりの大石垣が続きます。また、裏山の岩肌には県下では珍しい磨崖仏が彫られ、海抜500mの頂上近くには怪猫伝説を伝える八丈岩があります。